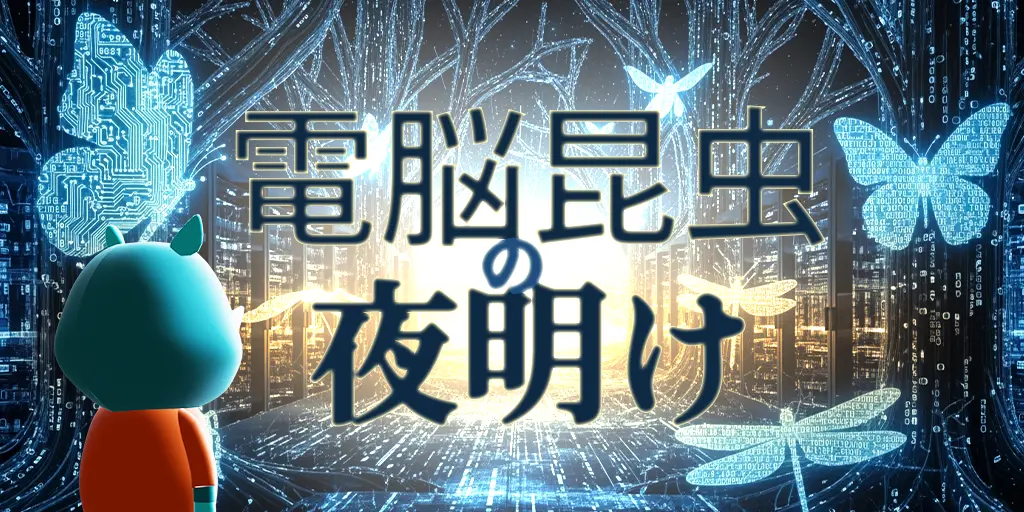沈黙する宇宙と、Web空間
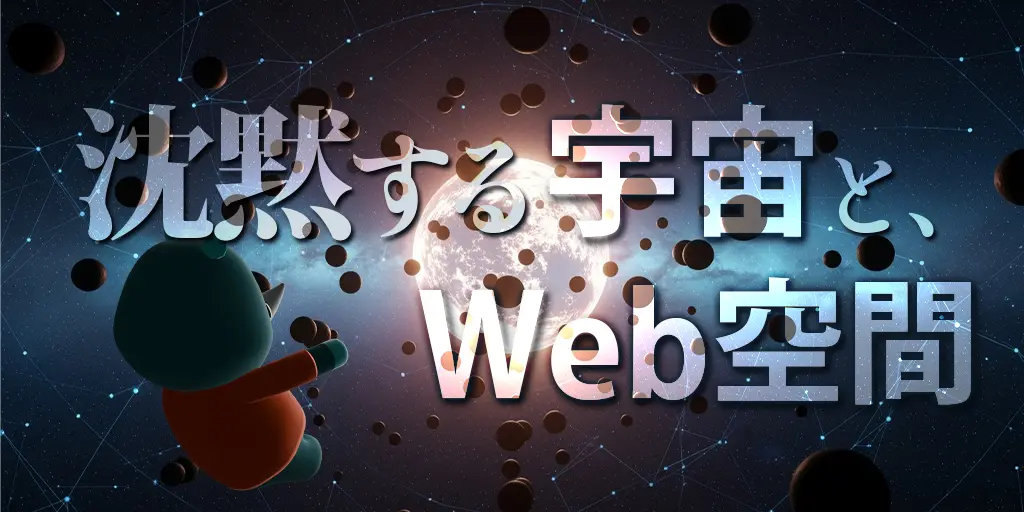
なぜ、誰もいないのか?
「宇宙に知的生命体が存在している可能性は高いはずなのに、なぜ我々は誰とも出会えないのか?」
これは1950年代に物理学者エンリコ・フェルミが口にした疑問であり、「フェルミのパラドックス」として今も科学者たちを悩ませ続けています。
星の数、地球に似た惑星の数、生命が生まれる条件は、統計的に見ても「孤独な存在」であるはずがない。
それにもかかわらず、私たちは宇宙からの明確な応答を受け取ったことがありません。
この“沈黙”の理由を、私たちは今、人工知能やWebの技術の中に見いだそうとしています。
AIは「沈黙」をどう捉えるのか
近年、NASAやMITなどの研究チームは、AIを用いて銀河スケールの文明拡散シミュレーションを行っています。そこでは、知的生命体の発生、拡大、消滅、通信の成立可能性などを数理モデルとして再現しています。
こうしたAIモデルから、次のような仮説が導かれています。
- 文明の寿命が短く、通信が成立する前に消滅してしまう
- 通信のタイミングがズレており、相手が発した信号に気づけない
- 高度な文明ほど、痕跡を意図的に残さない(沈黙を選ぶ)
AIはこれらの仮説を、もはやSF的な空想としてではなく、確率的に十分あり得る「現実の構造」として扱い始めています。つまり、フェルミのパラドックスにおける“沈黙”は、異常でも不自然でもなく、統計的にはごく自然な結果である可能性があるのです。
観測できないものは、存在しないのか?
フェルミの問いは、「観測されないものは存在しないのか?」という根本的な認識論にも関わります。
この問いは、AIが支配する現代のWeb空間でも、まったく同じ形で現れています。
AIによるユーザー理解や行動予測は、膨大なデータを前提としています。しかしそのデータには、重大な偏りがあります。
- よく発信し、よく反応する「目立つユーザー」の行動ばかりが学習材料になります
- 一方で、検索しかしない、投稿しない、購入しないが閲覧だけはする「静かな存在」は、ほとんど無視されてしまいます
その結果、AIの出す施策や広告、レコメンドは、主に「声の大きい人たち」だけに最適化され、確かに存在しているのに見えないユーザーが、無視されていくのです。
これは、宇宙における「信号を出さない文明」や「すれ違う通信」と極めて似た構造です。
AIは宇宙望遠鏡のように、観測できる範囲内の存在しか“認識”できないのです。
サイレントマジョリティの不可視性
マーケティングの世界には「サイレントマジョリティ(声なき多数)」という概念があります。
これは、実際に発言した人たちの意見が、そのまま全体の意見として扱われてしまう偏りを指します。
たとえば、SNS上である商品の評判が良いとしても、それはあくまで「発信した人たちの反応」にすぎません。
実際のユーザーの多くは何も言わず、沈黙したまま存在しているのです。
この“声なき多数”をAIが捉えることは困難であり、観測されないこと=存在しないことと誤認してしまう危険があります。
これはまさに、フェルミのパラドックスの本質と重なります。
沈黙とは、空白ではない
Webの中で何も発信しないユーザー、購買履歴を残さない閲覧者、アンケートに答えない支持層。これらは、データ分析上ではしばしば「ゼロ」として処理されてしまいます。
しかし、それは本当にゼロなのでしょうか?
それは、宇宙から信号が届かないからといって「知的生命体はいない」と結論づけることと、構造的に同じ過ちです。
AIにとって最も難しいのは、「沈黙」や「不可視性」に意味を見出すことです。
フェルミのパラドックスとは、単に宇宙の謎ではなく、見えていないものをどう理解するかという、知覚と技術の限界に挑む問いなのです。
沈黙は、不在ではない
フェルミのパラドックスは、私たちが宇宙で孤独かどうかを問うだけのものではありません。
それは、認識されない存在がどれほど多く存在しているかを再認識させる重要な視点でもあります。
- 観測されない存在は、本当に存在しないのか?
- データに現れないものを、どこまで技術で拾えるのか?
- 沈黙しているユーザーを、どう扱うべきか?
これらの問いは、AIが進化すればするほど、無視できないものとなっていきます。
宇宙もWebも、「沈黙しているから空である」とは限らないのです。
沈黙とは、空なる世界の、もっとも雄弁な声なのかもしれません。