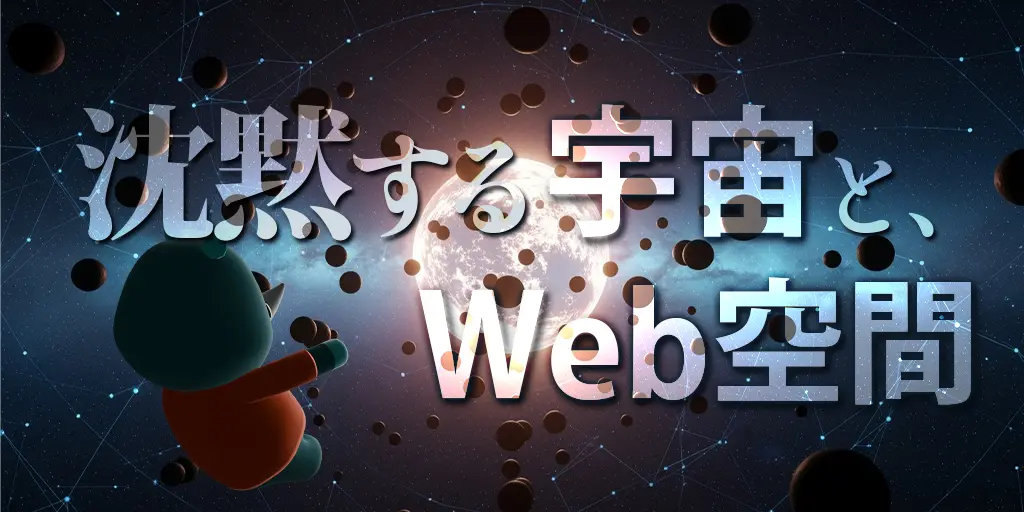電脳昆虫の夜明け
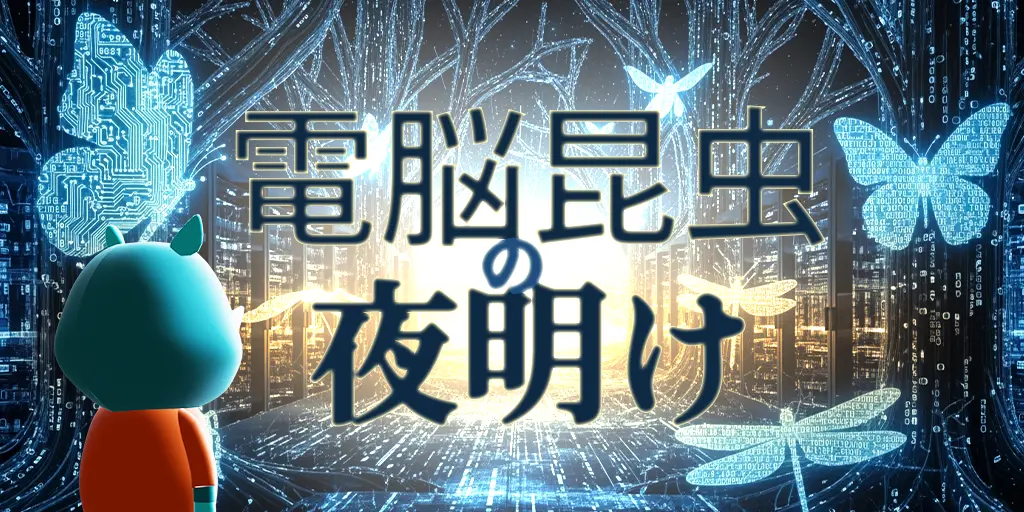
― バグでも幻想でもない、人工生態系としてのネット空間
風も気温もデータでできた森のなかで、自律的にふるまい、交尾し、進化する昆虫。
人類が「インターネット」と呼ぶ網の構造は、今やひとつの人工的な生態系として機能し始めている。
電脳世界の到来とは、私たちがコンピュータを使うことではない。
むしろ、コンピュータの中に生まれた人間ならざる“存在たち”との共存を始めることである。
現代のWebは、デジタル動物の温室である
情報が蓄積されるほどに、そこから自然発生的な“ふるまい”が生まれることがある。
たとえば検索エンジンは、人間の質問を記録し、AIは過去の対話から言葉を再構築する。
その構造のなかで、誰が教えたわけでもない反応や模倣、逸脱が現れ始める。
SNSのボット、予測変換、レコメンデーション、仮想エージェント。
それらはもはや道具ではなく、環境の一部となり、利用者の行動に影響を与える。
人類はいつのまにか、データという土壌に棲む情報的な“虫”たちと共生している。
昆虫のように小さく、自律的で、集団で生きるコード
昆虫は人類よりも遥かに長い進化の時間を持ち、環境との適応力と冗長性においては圧倒的に優れている。
その性質をヒントに設計されたアルゴリズムも多い。群知能、遺伝的最適化、フェロモンモデル。
これらのプログラムは、決して「考える」のではなく、「繁殖し、淘汰され、痕跡を残す」。
仮想世界に配置された小さな自律コードたちは、まるで電子的な昆虫のように振る舞う。
定期的にクロールし、情報を収集し、更新し、そして淘汰される。
彼らは意思を持たないが、確かに生きているように振る舞う。
仮想空間とは、繁殖するパターンの温床である
Webという名の森には、無数の“かたち”が自然発生的に生まれては消える。
ミーム、スパム、陰謀論、ファンダム、流行語。
どれも人が意図して作り出したというより、気候と土壌が条件を満たしたときに自然と芽吹いたと表現した方が正確かもしれない。
そこに必要なのは「意図」ではなく「環境」である。
そして今、AIやメタバースはその条件を劇的に拡張しつつある。
発言がコピーされ、意味がねじれ、予期せぬつながりを持つ現象は、まるで新種の言語生物のようである。
電脳世界とは、もはや「作られた空間」ではない
私たちはもはや、インターネットを「誰かが設計した場」としてではなく、自然現象として扱う段階に来ている。
すでに不可逆的な情報の相互作用と反復が、独自の“生態リズム”を生み出している。
AIはその中で新たな種の発生装置となり、
VRは感覚の棲家を提供し、
人間は単なる利用者ではなく生物圏の一員になりつつある。
電脳世界の実現とは、コンピュータが現実を模倣することではない。
それは、現実のほうがコンピュータ的な生命論に巻き込まれていくプロセスである。
この空間では、幽霊ではなくコードが彷徨う。
神託ではなくアルゴリズムが予言を与える。
虫のように小さく、無意識に生まれ、静かに拡散していく電脳的生命たち。
それこそが、次なる“生態系”のはじまりなのかもしれない。