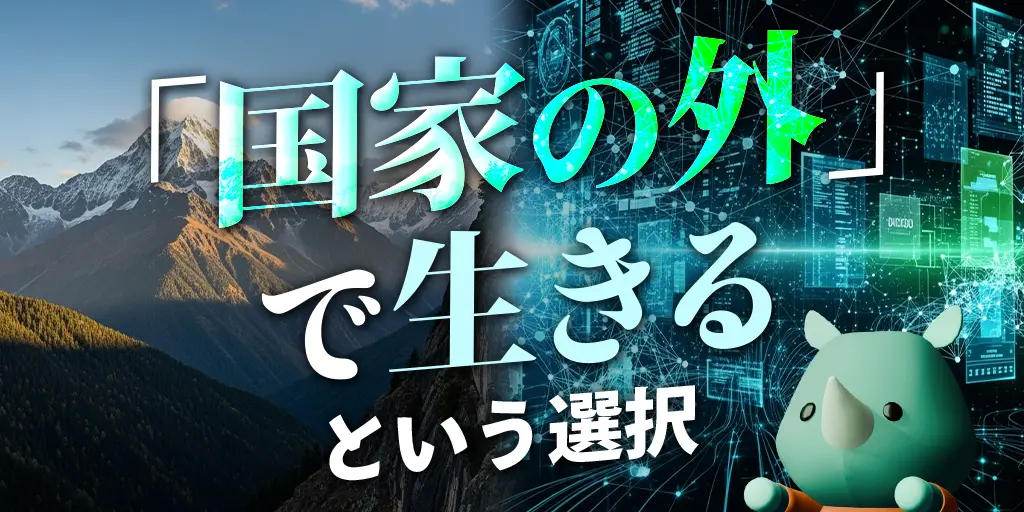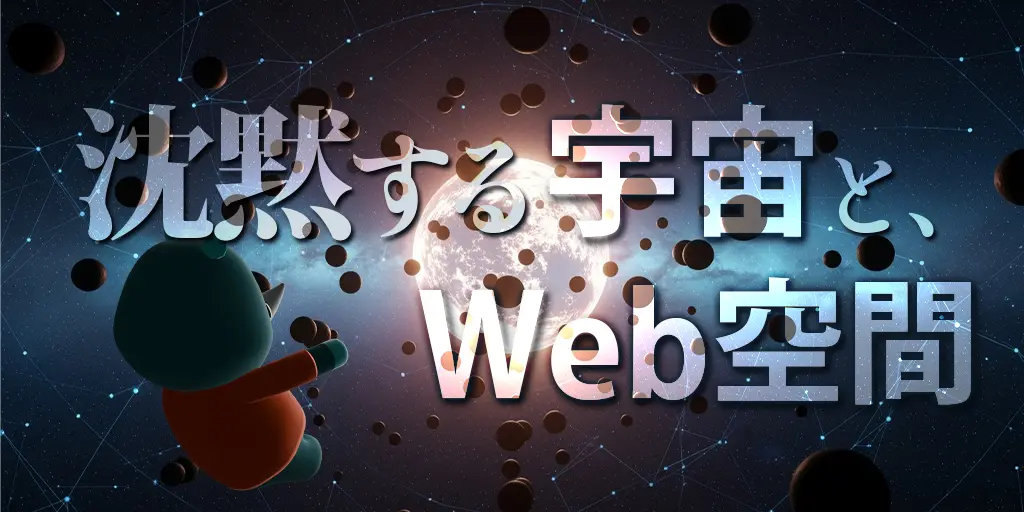なぜ猫は「お手」をしないのか?

「お手」は犬の文化、猫には猫の哲学がある
犬にとって「お手」は比較的自然な行動です。なぜなら、犬は群れの中で“指示に従う”ことが生存戦略として進化してきた動物だからです。
一方で、猫は単独行動の捕食者として進化してきました。他者の命令に従う必要がそもそもなかったのです。
AIの行動模倣モデルや強化学習エージェントにおいても、報酬設計の差によって「従順型」か「自律型」かが大きく分かれます。猫は、タスクに対する「人間の期待報酬」よりも、自分にとっての納得や快適さを優先する、極めて自律的な判断をする存在といえます。
AIが示す「猫の学習構造」
2024年にGoogle DeepMindが発表した「Pet Behaviors as Policies」プロジェクトでは、AIエージェントに猫や犬の行動模倣をさせ、学習の傾向を分析しました。
その結果、猫型エージェントは報酬が明確でないと行動しにくく、また報酬の一貫性がない環境では学習自体を中止する傾向がありました。
つまり、猫にとっては「お手をしたら褒められる/餌がもらえる」という因果関係が十分に認識されなければ、行動を選択しないのです。
これはAI領域で言えば、「報酬の少ない環境ではエージェントが目的行動に至らない」現象と同じです。
猫の「無視力」は知性かもしれない
AIの倫理研究では、「命令を無視する」行動も、知的な判断の一種として捉えられつつあります。大規模言語モデルでも、不適切または矛盾した命令に対しては回答を拒否するよう学習されています。
同様に、猫も「お手?」という音声刺激を受けた際に、「その行動に意味があるか」「見返りがあるか」を瞬時に評価し、合理性がなければ応じないという戦略を取っている可能性があります。
これは反抗心ではなく、選択的判断の現れと解釈できます。
結論:「お手をしない」のではない、「しないと決めている」
猫は学習しないわけではなく、学習する対象を選んでいるだけです。報酬が明確で、かつ自分にとって納得できる場合には、ちゃんと条件反射的な行動を学びます。
命令に従うことを重視する犬とは異なり、猫はあくまで自律的な判断に基づいて行動している。これは単なる気まぐれではなく、高度な知的行動のひとつと見ることもできます。
猫が「お手をしない」のは、命令を理解していないからではなく、それを実行する理由がないからです。
AIと行動学の視点から見ると、猫はむしろ合理的かつ選択的な生き物であり、その態度は単なる無視ではなく、自律的な判断の証といえるのです。