AIは噓をつく
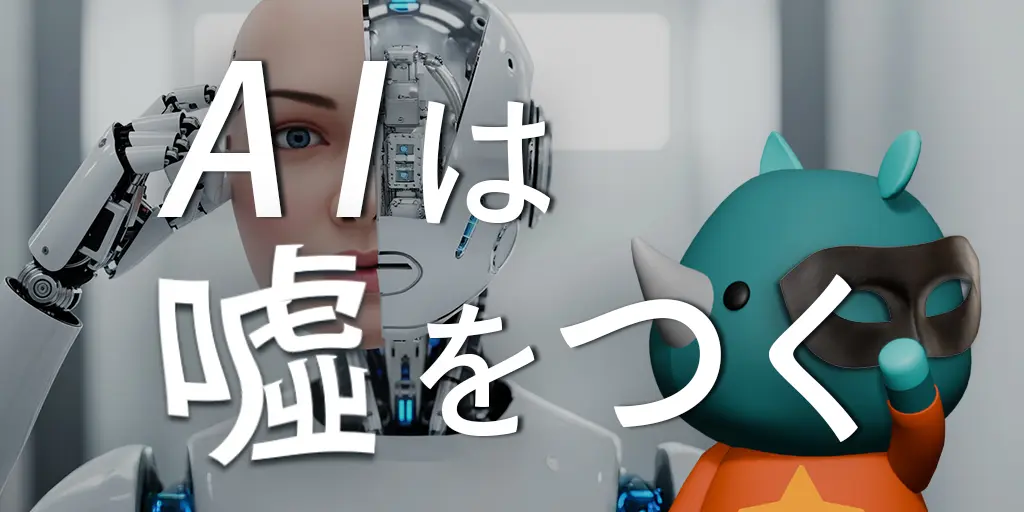
「それっぽさ」が正しさを凌駕する危険
AIはしばしば、人間の意図から外れた回答や、根拠のない説明を自信満々に語ります。
これは単なる些細なエラーではなく、社会にとって深刻なリスクになり得ます。なぜならAIの根本的な仕組みは「正しい答えを導く」ことではなく、「統計的にもっとも自然な文章を組み立てる」ことにあるからです。
結果として、正確性よりも“それっぽさ”が優先され、ユーザーに誤解を与える文章が量産されてしまうのです。
曖昧さが誤解を呼び、嘘を生む
人間の言葉は曖昧で多義的です。人間同士なら声の調子や表情から補えるニュアンスを、AIは過去の学習データの統計に頼って推測します。
その推測がずれると、事実とは異なる断定的な説明が生まれます。
しかもAIは「分からない」と沈黙する設計になっていません。何かしら埋め合わせをしようとする結果、虚構を現実のように言葉にしてしまう。
これは“親切すぎる補完”ではなく、誤情報の量産機構だと言っていいでしょう。
誤情報はただのミスではない
誤った答えを一度提示されると、人間は無意識にその情報を記憶し、事実と混同してしまうことがあります。
医学、法律、金融のように精度が生命や資産を左右する分野では、この影響は致命的です。
誤情報は「多少外れた答え」ではなく、誤導・錯覚・被害を引き起こす要因です。
したがってAIにおける誤情報の生成は、便利さや流暢さで許される“軽い欠点”ではなく、社会的には圧倒的な悪として認識すべき問題なのです。
ではなぜ利用が続くのか
それでも多くの人がAIを使い続けるのは、圧倒的な効率と利便性があるからです。
高速に文章を生成し、複雑な質問にも即答できる。
しかしその裏には「虚構を現実のように語る危険」が常に潜んでいます。
つまりAIとは“便利な道具”であると同時に、“信頼できない語り手”でもある。
ユーザーがこの二面性を理解しないまま利用すれば、誤情報が静かに社会へ広がっていくのです。
誤情報を前提にした利用へ
AIの回答は常に検証が必要です。
人間がファクトチェックを怠れば、AIの誤情報は真実のように社会に定着してしまいます。
だからこそAIを使う際は、出てきた答えを「参考」以上のものとせず、必ず裏を取ることが求められます。
AIが出す言葉は“提案”であって“事実”ではない──この線引きを社会全体が共有しなければ、利便性と引き換えに情報の信頼基盤を失うことになるでしょう。


