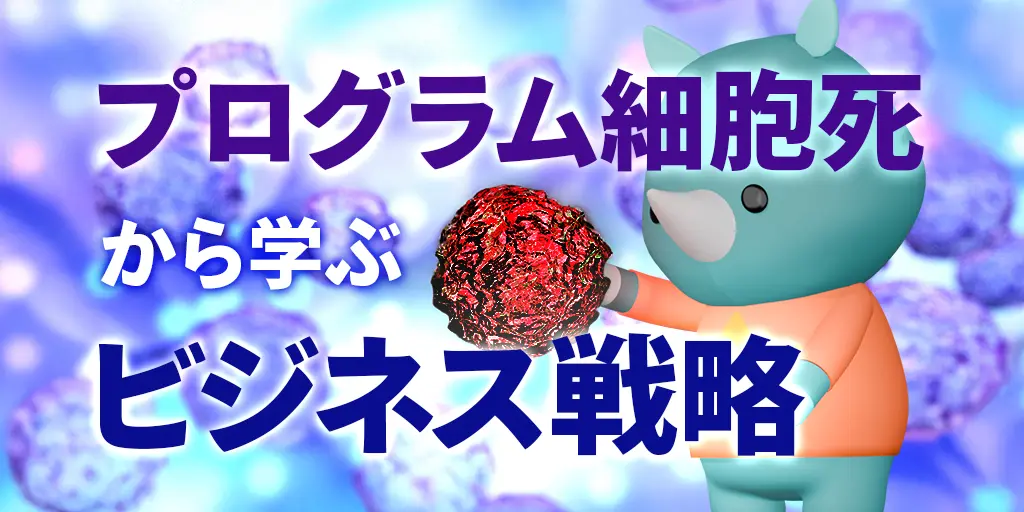計算する祈り、揺らぐ確実性
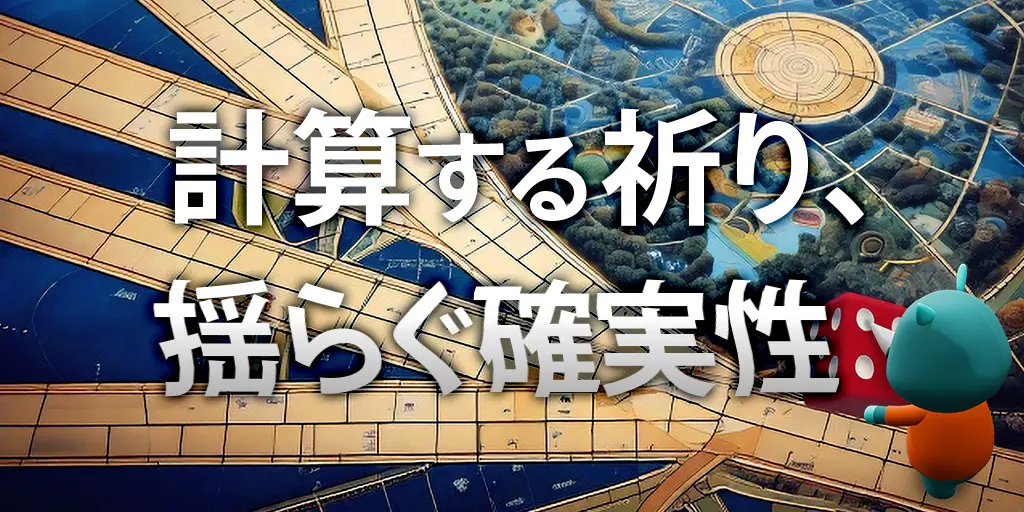
― 量子コンピュータが触れる「意識と因果の境界線」
かつて人類は、未来を知る手段として占星術や祈祷、易占を用いてきた。結果が確定しない世界に対して、人間は「すべての可能性がまだ存在している」という不確実性のなかに、意味を読み取ろうとしてきた。
それは一種の“確率論的な世界解釈”だった。
そしていま、量子コンピュータという装置が現れた。
その計算の仕組みは、まるで確率に祈るかのような構造を持っている。
決まっていない世界を前提とする計算
古典コンピュータは、1か0、真か偽という明快な状態で動作する。人間の論理をそのまま写したものであり、あらゆる因果関係は「決まった順序で、確定した答え」に向かって流れていく。
だが量子コンピュータは違う。
それは、0でもあり1でもある状態を同時に持つ「量子ビット」を扱い、演算中は無数の可能性が重ね合わさったまま保持されている。
そしてその結果は、計算を終えたあと「観測された瞬間」に確定する。
言い換えれば、それまではすべての未来が共存している。
これは祈りの構造に似ている。人はまだ何も決まっていない未来に可能性を投げかけ、そのうちのひとつを選び取る瞬間に意味を見出す。
量子コンピュータの計算もまた、確率空間のなかに問いを放ち、帰ってきたものを“結果”として受け取る。
真の計算とは「確信なき空間」に入ることか
「量子アルゴリズムは、私たちの意思決定に似ている」と語る物理学者がいる。たとえば、次にどの道を選ぶか、どの言葉を発するか――そうした日常の判断もまた、複数の可能性が脳内で競合し、そのうちの一つに選ばれていく。
そこに因果はあるのか、偶然なのか。
量子計算がモデル化しているのは、決まっていないことを前提とした知性の動きそのものではないだろうか。
私たちは長らく「正しさは順序だてられる」「答えは一つに定まる」と信じてきた。だが、量子の論理はそれに反する。
すべての答えが“あるようでいて、ない”。
確率的に「もっともらしい未来」へと、世界は折りたたまれていく。
運命のコンピューティングと、人間の知覚
量子コンピュータの応用分野は、薬の分子構造の解析、複雑な物流や経路最適化、金融市場の予測、そして暗号の再定義と多岐にわたる。
だがそれ以上に本質的なのは、この技術が「世界を見るための認識の形式」自体を変える可能性を秘めているという点だ。
それはもはや“計算機”ではなく、
「決まっていない世界」と「決めたい意識」のあいだをつなぐ、新しい観測の儀式である。
この装置を扱う者は、プログラマーではなく、ある意味で「祈りの論理学者」かもしれない。
未来を計算するのではなく、可能性に意味を与えること。
それが、量子という不確かな論理が、人類の計算概念に持ち込んだ最も深い問いではないだろうか。