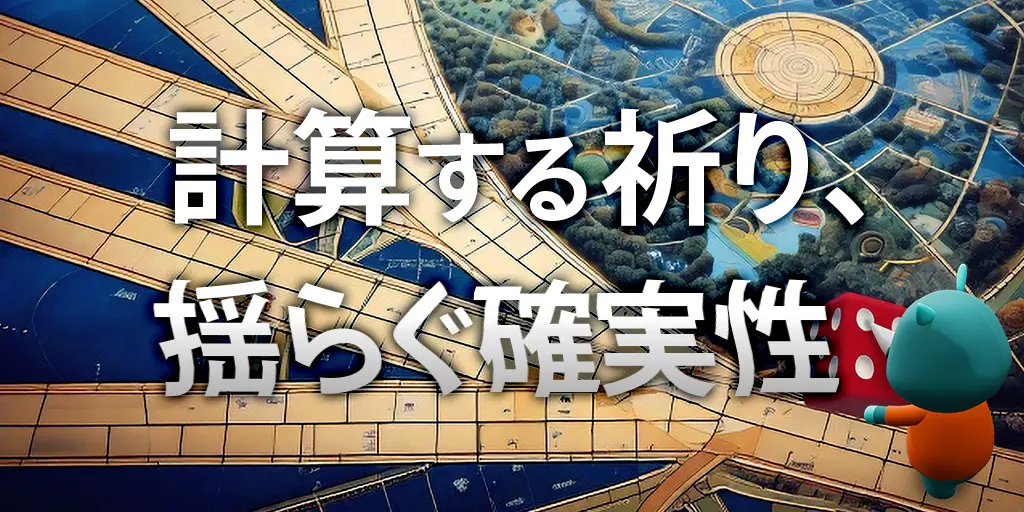感情をデザインする

― デジタル演出が心の“天気”を操作する時代へ
感情とは、内側から湧き上がる“自然なもの”だと私たちは思ってきた。
だがその自然は、案外もろい。
照明が変われば空気は変わり、色彩が変われば目の奥がざわめく。
たった一音のドローンノイズで、悲しさの輪郭はにじみ、心拍数が変わる。
それらを知ってしまったとき、ふと問い直される。
感情とは本当に“自分の中”にあるのだろうか。
それとも、演出された空間の中で“生まれるもの”ではないのか。
感情は「気象制御」されつつある
インスタグラムのフィルター、BGM付きの短尺動画、アルゴリズムが選んだサムネイル。
いまWeb空間の多くは、“感情が生まれやすい構造”に最初から設計されている。
悲しい投稿は「青っぽく」補正され、楽しい投稿は「暖色で」統一される。
AIによる音声合成は、共感のトーンを選択でき、UIは「泣ける」「エモい」といった既成感情ラベルを配布する。
私たちは知らぬ間に、「この気持ちはこういう色」「この場面にはこの空気」という半自動的な“感情テンプレート”の中に住んでいる。
それは、風景に照明を当てることで“天気”を操作するようなものだ。
感情は空から降るものではなく、舞台の上に設置されているものになりつつある。
情緒とは、演出装置の問題になった
都市の照明設計は、人の心理を計算に入れて作られている。
空港のゲートは緊張をほぐすために白昼光を使い、高級ブティックでは不安を忘れさせるようなディフューズな光が使われる。
同じことが、Web空間にも静かに進行している。
アプリの背景色、クリック音、ポップアップのタイミング。
それらはすべて、感情を「構成要素」として分解し、どの位置に、どの強さで、どの“心の装置”を配置すべきかという、一種の舞台装置としての設計論になっている。
デザインされるのは「泣き方」ではなく「泣きやすさ」
2020年代以降、AIによる生成メディアの浸透とともに、感情はコンテンツの「目的」ではなく、「素材」として取り扱われ始めている。
映画や小説の脚本すら、感情曲線に基づいて自動生成されるようになり、視聴者の顔の表情から、どの瞬間に涙腺が緩むかという統計が取られている。
これは感情のコントロールではなく、感情の構造化と“再現性の確保”である。
つまり私たちは、「この構図で、こういう音で、こういう速度で出せば、人はだいたいここで泣く」という“泣きやすさ”のテンプレートをもとに、作品を生産している時代に生きている。
感情はまだ、個人のものか?
それでも、感情は「人の中でだけ揺れる特別なもの」なのだろうか。
もし涙を誘う照明設計があり、怒りを導く音響演出があり、共感を生むUI配色があるとすれば、感情は“内側”ではなく“配置”によって生まれる仮象ではないか。
それは決して否定的な意味ではない。
感情がデザインされうるということは、「感じさせたいこと」を届けるための美術的・構造的手段が可能になったということでもある。
感情はもう、制御できない嵐ではない。
それは気圧や湿度のように、設計可能な“空間的なもの”になってきたのだ。