「ねこですよろしくおねがいします」

― 名を変えても、その本質は変わらない ―
"What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet."
『ロミオとジュリエット』 第2幕 第2場
名前が違っても、バラは同じ香りがする。
――黒猫にも、同じことが言えるだろう。
その毛並みも、歩く姿も、古代から変わっていない。
変わったのは、黒猫を見つめる人間である。
神の使いとしての黒猫
古代エジプトにおいて、黒猫は家庭と生命を守る女神バステトの象徴だった。
家庭を豊かにし、病を退ける守護の存在。
神殿には黒猫の像が並び、奉納や弔いの儀礼まで整っていた。
夜に輝く瞳やしなやかな動きは、神聖さと力強さの表れだった。
この時代、黒猫は畏敬の対象であり、「不吉」などという概念すらなかった。
魔女の影に隠された黒猫
ところが中世ヨーロッパに入り、情勢は一変する。
キリスト教が広がり、異教の風習や自然信仰が「悪魔的」と再定義された。
その中で、夜行性で人に懐きにくい黒猫は魔女の使い魔(familiar)とされ、
悪魔と通じる存在とみなされた。
「黒い=闇」「夜=悪」「独立した存在=危険」という連想は、
社会が“見えないもの”を恐れる心理の裏返しだった。
そして、魔女狩りの時代に黒猫はその象徴となった。
不確かな噂や宗教的偏見が、無垢な動物を「不気味な存在」に変えたのである。
迷信と逸話の狭間
中世ヨーロッパでは、黒猫にまつわる数多の逸話が生まれた。
その中でもよく知られているのが、「猫が迫害された結果、ネズミが増え、ペストが流行した」という物語である。
人々が黒猫を“悪魔の使い”として恐れ、次々に殺したために、
疫病を運ぶネズミが繁殖し、結果として黒死病が猛威を振るった――そんな筋書きだ。
しかし実際には、これを裏付ける史料はほとんど存在しない。
猫が一部の地域で嫌悪や迫害の対象となった記録はあるものの、
それがペスト拡大の直接要因となったという確かな証拠は乏しい。
この因果関係は、歴史的事実というより後世の寓話的脚色に近いと考えられている。
それでもこの逸話が今なお語り継がれるのは、そこに人間の心理的な真実が潜んでいるからだ。
人は見えない恐怖に直面したとき、理解の及ばない災厄を「わかりやすい敵」に置き換えようとする。
複雑な現実を単純な物語に還元し、
恐れの矛先を外に定めることで、不安を一時的に“制御できた気になる”のだ。
人々は自らが生み出した恐怖を黒猫に押しつけ、
やがてその報いのようにペストが蔓延すると、
今度はその災厄の責任さえも黒猫に擦り付けようとした。
神秘と幸運の狭間
そして近代以降、黒猫のイメージは再評価されていく。
アメリカでは「黒猫が家に入ると幸運が訪れる」という地域伝承もあり、
海上では船乗りたちが「黒猫を乗せると航海が安全になる」と信じていた。
黒猫は不吉の象徴であると同時に、守護と繁栄のしるしとしても受け取られるようになった。
やがて19世紀末から20世紀にかけて、黒猫は芸術とファッションの世界で独自の地位を得る。
フランス・モンマルトルのキャバレー「ル・シャ・ノワール」のポスターは、
退廃と自由、夜と芸術を象徴するアイコンとしてパリ文化を彩った。
黒という色が持つエレガンスや神秘性が、黒猫の輪郭をより際立たせたのだ。
現代においてもその存在感は衰えていない。
美術館やファッション、広告のモチーフとして黒猫は頻繁に登場し、
そのシルエット一つで“夜の静寂”“孤高の知性”“見えない力”といった概念を想起させる。
かつての恐怖の象徴は、いまや洗練と美の象徴へと変わった。
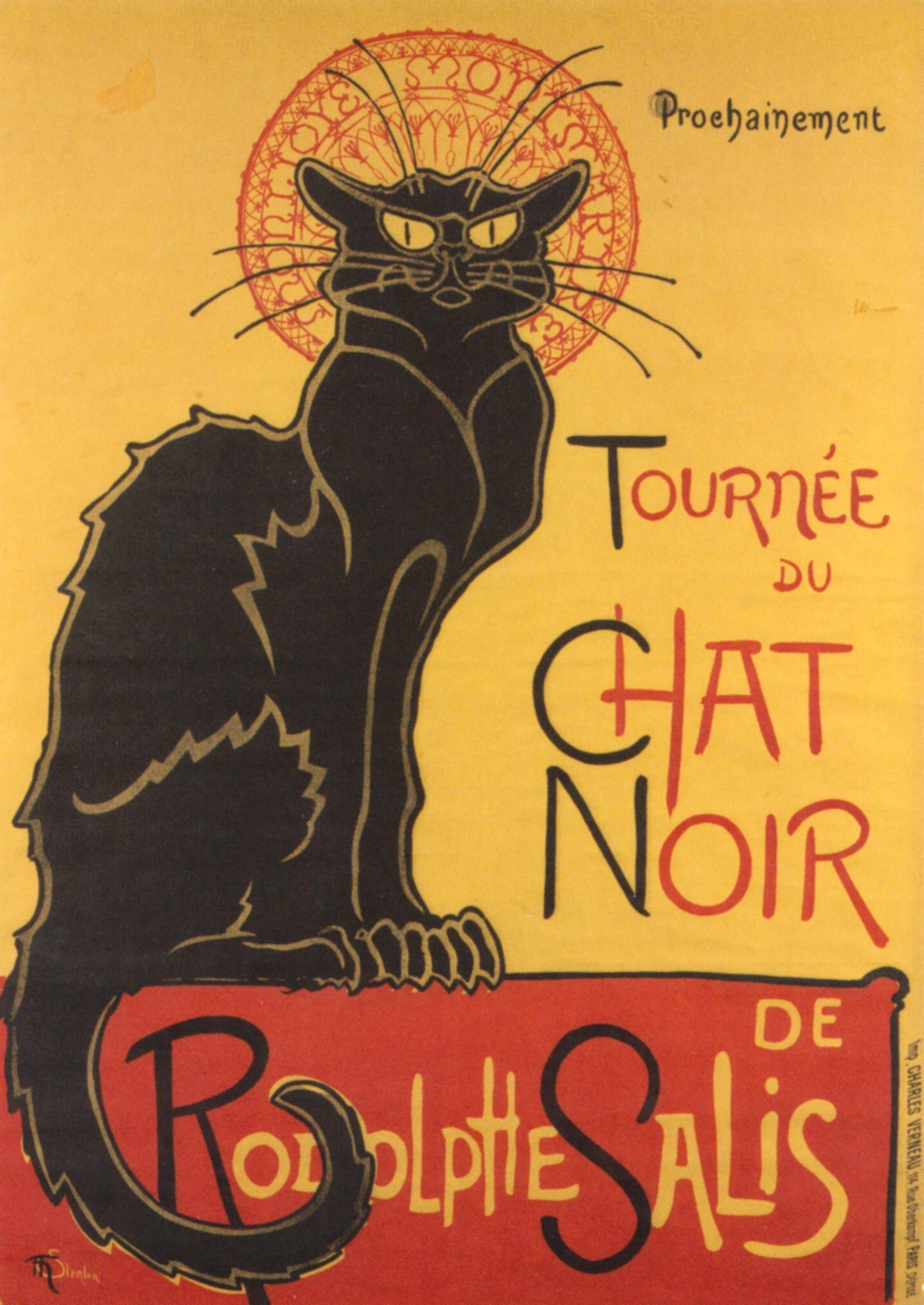
認識を操るという危うさ
こうして振り返ると、黒猫を取り巻く物語は、常に情報の力によって形づくられてきた。
宗教、噂、メディア――それらが放つ言葉やイメージが、
同じ存在を「神」とも「悪魔」とも描き分けてきたのだ。
どんな時代にも、物語を操作できる者が現実の意味を塗り替える。
黒猫は、その構図の犠牲者であり、同時に証人でもある。
黒猫がいる。
黒猫の目は光を反射して輝くだけ。
そこに何を見るかは人間の心が決める。
黒猫は変わらない。
変わるのは、いつの時代も人間の認識なのだ。
そしてその認識を左右するのは、「情報」である。
静かな瞳で夜に溶け込む黒猫は、
人間が作り上げる物語を、黙って見つめ続けている。


