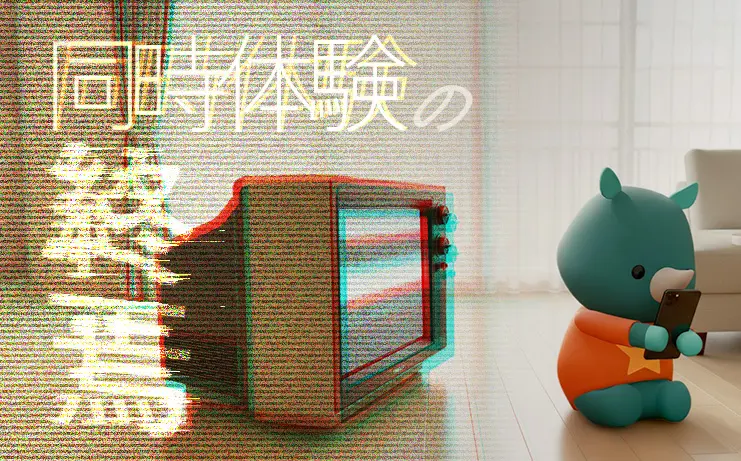甘いチョコレートの香りが街を包み、恋人たちが愛を語らう2月14日。
現代において、バレンタインデーは純愛と幸福の象徴である。
しかし、この祝祭の皮膜を一枚めくれば、そこには現代の倫理観では到底受け入れがたい、血生臭く、そして野蛮な「残酷な起源」が横たわっている。
我々が信じるロマンチックな物語の裏側に隠された、獣臭い暴力の歴史を紐解いていく。
荒れ狂う獣の祭り「ルペルカリア祭」
バレンタインデーの遠い祖形とされるのは、古代ローマで行われていた「ルペルカリア祭(Lupercalia)」である。
毎年2月13日から15日にかけて開催されたこの祭りは、現在の甘美な雰囲気とは対極にある、荒々しく暴力的な豊穣祈願の儀式であった。
祭りの主役は「ルペルキ」と呼ばれる、選ばれた貴族の青年たちである。
儀式は、ローマ建国の祖であるロムルスとレムスが雌狼(ルパ)に育てられたとされる聖なる洞窟「ルペルカル」で幕を開ける。そこで執り行われるのは、神への生贄だ。
祭司たちは山羊と犬を屠り、その血を若い男たちの額に塗りつける。
そして、その血をミルクに浸した羊毛で拭い去った瞬間、青年たちは高笑いを上げなければならなかった。
この不気味な儀式は、文明が獣の野生を克服し、再生することを象徴していたとされる。
だが、真の「残酷さ」はその後に待っていた。
豊穣という名の暴力
生贄となった山羊の皮を剥ぎ、細長く切って鞭(フェブルア)を作ると、青年たちは下半身にその皮を巻きつけただけのほぼ全裸の状態で、街中へと駆け出していく。
これが祭りのクライマックスである。
彼らは手に持った山羊皮の鞭で、道ゆく人々を、特に若い女性たちを容赦なく叩き回った。
現代の感覚からすれば狂気の沙汰であるが、当時の女性たちは進んでその鞭の前に身を差し出したという。
この鞭打ちを受けることで「不妊が治る」「安産が約束される」と信じられていたからだ。
「フェブルア(februa)」という言葉はラテン語で「浄化」を意味し、2月(February)の語源となった。
つまり、2月とは本来、チョコレートを贈る月ではなく、生贄の血と山羊の皮で人々を「浄化」し、強制的に豊穣を促す暴力的な月だったのである。
「くじ引きマッチング」
このルペルカリア祭において、起源の闇を象徴するエピソードとして語り継がれているのが「くじ引き」だ。
祭りの期間中、若い女性たちが自分の名前を書いた札を壺に入れ、それを男性たちが引き当てる。
選ばれたペアは、祭りの期間中――あるいはその後の一年間――性的なパートナーとして過ごすことを義務付けられていたという。
近年の歴史学において、この「くじ引き」の具体的な記録が古代ローマ側に乏しいことから、その実在を疑問視する声があるのは事実だ。
しかし、見逃せない点がある。後世のキリスト教徒たちがこの祭りを「風紀を乱す野蛮極まりない行事」として糾弾する際、このエピソードが格好の標的として執拗に強調されたという事実だ。
キリスト教側がこれほどまでに嫌悪し、記録に刻み込もうとした背景には、単なる創作を超えた「何らかの事実」があったと考えるのが自然だろう。
たとえ整った「くじ引き」という形式ではなかったにせよ、祭りの狂乱の中で、女性の意志を無視した強引なペアリングや、行きずりの性的結合が日常的に行われていた可能性は極めて高い。
愛のない結合、そして公衆の面前での暴力的なマッチング。
それは、現代の「自由な恋愛」の対極に位置する、文字通りの「残酷な偶然」による支配だったのである。
聖ウァレンティヌスの処刑とすり替えられた神話
この異教の野蛮な祭りを、キリスト教的な「聖人の祝日」へと作り変える動きが出たのは、5世紀末のことである。教皇ゲラシウス1世は、ルペルカリア祭を禁止し、代わりに2月14日を「聖ウァレンティヌス(バレンタイン)の日」と定めた。
聖ウァレンティヌスその人の伝説もまた、残酷な結末を伴う。
時の皇帝クラウディウス2世は、兵士たちが家族を恋しがって戦力が低下することを恐れ、若者の結婚を禁止していた。
ウァレンティヌスはその禁を破り、密かに恋人たちの結婚式を執り行っていたために捕らえられ、処刑されたという。
ここで重要なのは、教会が「暴力的な豊穣祭」を上書きするために、「愛のために殉教した聖人」という物語を利用したという点だ。
山羊の鞭で女性を叩く祭りは、いつの間にか「愛の守護神」を称える日へと巧妙にすり替えられた。
しかし、その根底には、異教の神々に対する教会の激しい拒絶と、血の歴史が流れている。
残酷さを隠す「甘いベール」
バレンタインデーが現在のような「恋人たちのロマンチックな日」として確立されたのは、さらに後の時代、14世紀の詩人ジェフリー・チョーサーの影響が大きい。
彼は自らの詩の中で「聖バレンタインの日に、鳥たちが番(つがい)を求めて集まる」と記し、この日を自然界の愛の始まりと結びつけた。
中世の騎士道物語や宮廷恋愛の流行が、この「愛の日」というイメージをさらに増幅させた。
そして19世紀、産業革命とともにグリーティングカード(現代の「チョコを贈る」という習慣が定着する前、欧米でのバレンタインの主役は「カードを贈ること」だった)の量産が始まり、20世紀にはチョコレート業界の巧みなマーケティングが加わることで、かつての「血と獣の匂い」は完全に消し去られた。
現代のバレンタインデーにおいて、山羊の生贄を思い浮かべる者は一人もいない。人々が手にするのは、血に染まった鞭ではなく、丁寧にラッピングされたチョコレートである。
忘却と救済
ルペルカリア祭の残酷な儀式、強制的なカップリング、そして聖人の処刑。
バレンタインデーの起源は、どこを切り取っても「痛み」と「強制」に満ちている。
しかし、歴史とは皮肉なものだ。本来、女性への暴力や非自発的な結合を内包していた祭りが、数千年の時を経て、女性が主体的に想いを伝え、愛を享受する文化へと180度転換したのである。
我々は、過去の残酷さを忘却することで、この日を「幸福な一日」へと昇華させた。
もし、2月14日の夜に不思議な寒気を感じたなら、それは古代ローマの青年たちが振り回した山羊の皮の風かもしれない。
我々が享受する「愛の祝祭」は、かつて流された血の上に築かれた、奇跡的なまでの虚構なのである。