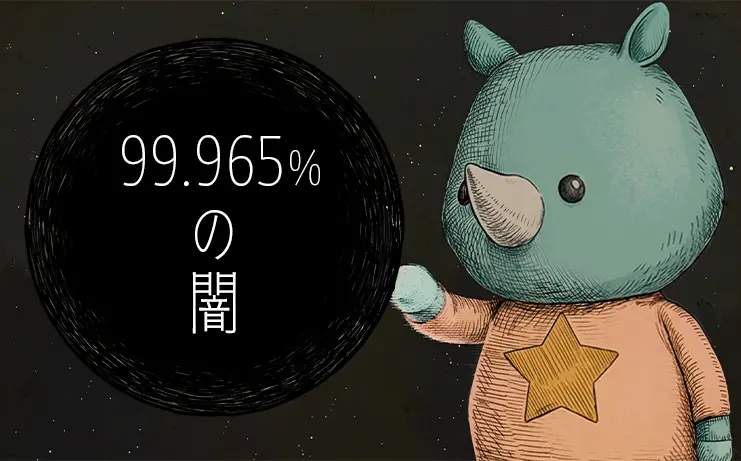光をほとんど吸い尽くす黒い塗料がある。
可視光の99.965%を吸収する――ベンタブラックだ。
2014年、英国サリー・ナノシステムズ社はこの物質を開発した。
カーボンナノチューブで形成された迷路のような構造に光が入ると、無数の屈折を繰り返し、ほぼすべてが熱として吸収される。
立体物に塗布すると、陰影も奥行きも消え、まるで現実に「穴」が空いたかのように見える。
この素材は当初、衛星搭載の黒体校正用に開発された。
だがその後、宇宙産業、軍事、光学設計、高級時計の文字盤、
そして2019年にはBMWの特別仕様車X6にも採用されるなど、予想を超える広がりを見せた。
それでも開発者は言う。
「正しい使い道は、まだ分からない」
ベンタブラックは、用途が定まらないまま圧倒的な力を手に入れてしまった例だ。
そして今、私たちはそれと似た状況にある。
思考を超える計算
2024年以降、生成AIの普及は一気に加速した。
ChatGPT は全世界で月間利用者が10億人を突破し、Google の Gemini も数億人規模のユーザーを抱える。
中国の大手プラットフォームや独自言語モデルを含めれば、AI利用者は数十億人規模に達していると推定されている。
AIはもはや一部の専門家だけの道具ではなく、人類全体のインフラへと大きく変貌した。
人工知能は、画像、音声、文章、行動ログといった異なるデータを同時に解析し、相関を見つけ、予測モデルを構築する。
人間が一生かけても処理できない情報を、AIは瞬時に読み解く。
だが、ここで決定的な問題が顕在化している。
AIの判断を説明できないという事実だ。
説明なき判断
2016年、囲碁AI「AlphaGo」が世界トップ棋士を破ったとき、研究者や棋士は驚嘆したが、戦略の根拠を説明できなかった。
AIは盤面における最善の一手を示したが、なぜその手が最善なのかを解き明かすことはできなかった。
この「ブラックボックス性」は、現在のあらゆるAIに共通する特徴である。
出力される結論は高精度だが、その背後にある判断基準を人間が完全に説明することはできない。
成果は得られる。
しかし、意味づけが追いつかない。
私たちは今、まさにその段階にいる。
技術は常に理解より先に進む
歴史を振り返れば、この構図は初めてではない。
蒸気機関は熱力学が体系化される前に産業を変えた。
電気は電磁気学が整う前に都市を照らした。
原子核反応は制御理論が追いつく前に兵器として実装された。
技術は常に、「これは何に使えるのか」「どこまで許されるのか」という問いを、後から人間に突きつけてきた。
人工知能もその一つである。
データは単なる記録ではない
データはもはや情報の痕跡ではない。
気候や地形と同じように、存在するだけで世界の動きを変える環境要因になっている。
巨大テック企業には、行動履歴、消費傾向、嗜好や関心の遷移が集積され、AIはそれを学習基盤としている。
これらは単なる数値ではない。
個人と社会の振る舞いを高次元で表すパターンである。
この状況を問題視する声の一方で、Web3や分散型技術への関心が強まっている。
ブロックチェーン、自己管理型アイデンティティ、分散型自律組織(DAO)。
これらは、中央集権的なデータ統合への反動ではなく、データのあり方そのものを問い直す動きだ。
分散が正解か否かは別として、
データの支配構造が社会的な価値判断の対象になったという事実は重要である。
私たちはどこまで委ねられるのか
人工知能はすでに、医療診断、金融審査、自動運転、創作支援、政策提言支援などに深く関与している。
画像診断AIは人間の専門家を上回る精度を示し、自動運転は人間よりも瞬時の判断を下す。
しかし、AIの判断プロセスが不透明である限り、
その結論に責任を負うのは誰なのかという問いは、制度・倫理・実務のすべてにおいて解決されていない。
この問題に対応するため、XAI(説明可能なAI)の研究が進んでいる。
AIがどのようにして結論に至ったかを、人間に理解可能な形で提示する試みだ。
さらにEUは一般データ保護規則(GDPR)で「自動意思決定に関する説明を受ける権利」を定め、
日本でも「人間中心のAI社会原則」が掲げられている。
だが、この一連の動きを、AIに深く関わる人間が見れば、
おそらく静かに苦笑いするだろう。
数億、数千億のパラメータを持つモデルに対し、
「なぜそう判断したのかを説明せよ」と求めることが、
どれほど表層的な要求であるかは、現場にいる者ほどよく知っている。
多くの場合、これは技術的な対話ではない。
政治的な安心材料であり、
制度を整えているという「姿勢」を示すための言葉に過ぎない。
一部の利害関係者にとっては意味を持つかもしれない。
だが、AIの本質的な挙動や、
人間の理解を超え始めた計算の現実に対して、
どこまで実効性があるのかについては、
すでに多くの人が気づいている。
説明を与えることで制御した気になる。
理解したという物語を用意することで、
不安を棚上げにする。
それ自体が悪いわけではない。
だが少なくとも、それが問題の核心ではないこともまた、
誰の目にも明らかになりつつある。
極北の果て
ベンタブラックは、「黒を極限まで追求する」という純粋な動機から生まれた。
用途は後から追いつき、意味は時間をかけて社会にもたらされた。
人工知能も同じだ。
最初から完全な使い道を設計することはできないし、
むしろ早急に意味づけしようとすることの方が危うい。
私たちは今、
意味や用途が理解の前に手に入ってしまった技術を扱っている。
拡散、浸透、超越
2025年は、
人工知能が「選択肢」ではなく「前提」へと変わった年として記憶されるだろう。
蒸気機関には数十年、
電気には数十年、
インターネットには二十年近い時間が必要だった。
生成AIが社会の主要インフラになるまでの時間は、わずか数年だった。
進化の速度は、人類の適応速度を追い越しつつある。
だがそれは、恐れるべきことではない。
未知を抱えたまま進む
もし、光を100パーセント吸収する物質が生まれたとき、
私たちはそれを何に使うのだろうか。
それは意図を伴って使われるのか、
あるいは、価値が分からないまま「見せるため」に消費されるのか。
同じ問いが、人工知能にも突きつけられている。
思考も、意味も、経験も、判断も、
すべてを吸い込み、
人間より速く、深く、静かに結論を出す存在を、
私たちはどこまで、その手綱を握り続けることができるのだろうか。
私たちはテクノロジーを生み出しているつもりで、
実のところ、その巨大な力に
ただぶら下がっているだけなのではないか。
光を呑み込む黒の前で、
思考を超える計算の前で、
私たちはいま、自分たちの立ち位置を問われている。
この先にあるのが闇なのか、
それとも、新しい風景なのか。
それを決めるのは、
技術ではない。
問い続けることをやめた瞬間に、
答えは、すべて吸い込まれていく。